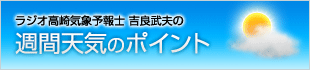土屋 文明
つちや ぶんめい(1890~1991)
百歳まで輝き続けた歌の巨人
~柿本人麻呂・斎藤茂吉と並ぶ日本三大歌人~
 土屋 文明
土屋 文明
多感な少年時代を過ごした保渡田
土屋文明は、明治、大正、昭和、平成を生き、100歳の生涯を閉じるまで12,300余首を残した近代日本の代表的歌人で、優れた万葉学者です。
明治23年に現在の高崎市保渡田町(当時:西群馬郡上郊村保渡田)の農家に生まれました。家は貧しく、子供のない伯母のぶの嫁ぎ先・福島周次郎の家で、3歳から高崎中学卒業まで過ごしました。
文明は祖父藤十郎について「賭博で身を持ち崩した揚句、強盗の群に身を投じ、徒刑囚として北海道の監獄で牢死した」と述べています。そのせいで、一家に続けられる村人の指弾は、文明にとって耐えがたく、この前後数年間は、道で村人に逢うのも恐ろしかった」といいます。父の保太郎も村に居づらかったのか、村を出入りして商売をしていました。
村上成之、伊藤左千夫...
出会いによって開かれた運命
晩年の『自伝抄』で、小学校卒業後は、高崎の薬屋に小僧として住み込むことになっていたが、卒業の前になると、中学校の入学試験を受けてみろということになったと記しています。福島周次郎の家の半分を借りて住んでいた塚越通三郎、中沢愛之祐、関根甚七などの教師たちが、文明の抜きん出た素質のために取り計らったようです。
高崎中学入学の前後、中沢愛之祐先生から「ホトトギス」が送られ、初めて正岡子規を知り写実主義の重要さに目覚めました。「ホトトギス」に投句していた文明は、「アララギ」の前身「アカネ」を知り、短歌の投稿を始めます。そのころ、国漢の教師として村上成之が赴任してきます。成之は村上鬼城と交流し、伊藤左千夫とも親交があった俳人、歌人です。
卒業を前に文明は、東京での文学活動を志し、その頃東京の茅場町で搾乳業を営んでいた伊藤左千夫の牛舎で働かせてもらおうと、成之に口添えを頼みました。
働き始た文明に対して、その才能を惜しんだ左千夫は第一高等学校への進学を勧め、資産家の寺田憲と医師の小此木信六郎に学資の工面も頼んでくれました。
文明が一高を卒業した大正2年に左千夫が急死し、文明は棺にすがって夜通し泣き続けたといいます。
結婚、信州での教職
東京帝国大学哲学科を卒業した文明は、信州の教育界に6年間身を投じました。赴任直前に、在学中から心を通わせた塚越テル子と結婚します。
テル子は明治19年生まれ、同郷の保渡田の名士の家柄で、キリスト教に入信し、高崎教会の会員でもありました。女子英語塾(津田塾)を卒業後、足利高女の英語教師となりました。早世した文明の初恋の少女の姉でした。
「アララギ」の支柱として活躍
疎開、大切な人の死
斎藤茂吉から編集発行人を引き継ぎ、「アララギ」の指導的存在となり、その企画力、組織力は長くアララギの新しい土壌を培いました。
昭和20年に戦災で南青山の自宅が焼失し、吾妻郡原町(現東吾妻町)川戸で約6年半の疎開生活を送ります。この間、『万葉集私注』の執筆、「アララギ」の復興、アララギの地方誌の育成など精力的に活動しました。
昭和26年11月、文明は南青山に帰住。昭和28年に、宮中歌会始の選者になり、『万葉集私注』により芸術学院賞を受賞しました。
文明の単独の歌集『青南後集』には、人生最大の悲しみが詠われています。昭和49年6月に長男夏実を、57年4月に、妻テル子を亡くしました。
終わりなき時に入らむに束の間の
前後ありやありて悲しむ
百年はめでたしめでたし 我にありては 生きて汚き百年なりき
平成2年9月、文明は100歳を迎えました。10月、代々木病院に入院しベッドの上での生活となりました。付き添った息女草子に話すことは故郷・上郊村のことばかり。そして、眠りから覚めた文明の「ああ生きていたか、ありがたいなぁ」という言葉を幾度も聞いたといいます。文明は同年12月8日、心不全で亡くなりました。
文明と親交もあり、歌人で群馬ペンクラブ会長を務めた原一雄は「古今を通じて短歌の上に最も秀でた三人は、柿本人麻呂と斎藤茂吉と土屋文明」と記しています。文明はまさに歌の巨人でした。
想い続けた故郷 永久の幻・榛名山
 文明の歌碑(群馬県立土屋文明記念文学館の敷地内)
文明の歌碑(群馬県立土屋文明記念文学館の敷地内)
 文明が好んで食べたカステラとミルクティー。土屋文明記念文学館には文明の書斎が移築保存されている。
文明が好んで食べたカステラとミルクティー。土屋文明記念文学館には文明の書斎が移築保存されている。
榛名丘陵に広がる桑畑、井野川や沢でドジョウやカニを取った原風景が、文明の中にありました。文明の人間愛、やさしさ、激しさ、厳しさ、寂しさは、こうした風土に育まれました。冒頭に記した生い立ちによって、故郷は辛く悲しい場所でもあり、高崎中学を卒業し上京して以来、数えるほどしか、故郷の土を踏みませんでした。
道の上の古里人に恐れむや
老いて行く我を人かへりみず
この歌を作ったのは、文明が61歳のときです。幼い思い出のように古里人に恐れを抱いています。
生前、自身の歌碑を許さなかった文明が、唯一認めた歌碑が、死の直前の平成2年9月5日に除幕されました。
青き上に榛名をとはのまぼろしに
出でて帰らぬ我のみにあらじ
この句が刻まれた歌碑は、土屋文明記念文学館の敷地内にあります。文明は、群馬町の名誉町民になったことを最も喜びました。100歳の生涯の中でその心に思い続けたのは、榛名山でした。
※参考資料 「土屋文明私観」(原一雄著)
「歌人土屋文明」(土屋文明記念文学館)
「土屋文明ひとすじの道」(土屋文明記念文学館)