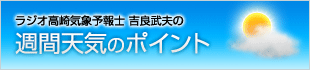たかさき町知るべ
並榎町(なみえまち)

市街地の北西部に位置している町で、北から東は大橋町、西は上並榎町と烏川対岸の下豊岡町、南は烏川原、東は台町と歌川町となっている。
「並榎」の地名は古く、安貞元年(一二二七)の『法然上人絵伝』(『高崎市史』資料編4、中世Ⅱ所収)に「上野国より登山し侍(はべ)りける並榎の賢者定照」があり、鎌倉時代のはじめ近くまでさかのぼることができる。町名の由来は、榎(えのき)が多く並ぶように自生していたことによるといわれている。
「並榎」は次第に大きく発展し、上下二つに分村したが、その時期がいつであったのかはわからない。明治二二年(一八八五)「西群馬郡高崎駅」は「高崎町」となったが、このとき「下並榎町」は、下和田村、赤坂村とともに高崎町に合併し、「上」がないのであるからとの理由で、「下」の字をとり、「並榎町」となった。
町の南西方の字「幅(はば)」地内からは、弥生時代中期の遺跡が発見調査されている。また、町の西方に字「修理免(しゅうりめん)」があるが、これは、下並榎村当時、村内にあった社寺、念仏堂などの修理費を出すための、免税共同耕作地からつけられた名である。
曹洞宗の常仙寺(じょうせんじ)は、明治七年開校の上・下並榎村共立の小学校に充てられた。
明治、大正期のこの町は、閑静な田園地帯で、住宅地として次第に人家が増えてきたところである。俳聖とたたえられた村上鬼城も晩年はこの町で過し、自らは居宅を「並榎村舎」と称していた。