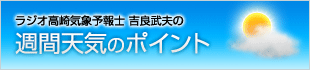ちょんまげ時代の高崎
第十一話 家老の子は家老

私は位牌が残っている堤家系図から言えば十三代にあたる。"知恵伊豆"と称され、三代将軍の参謀に当たる老中を務めた松平伊豆守信綱公から、五男の信興公が茨城県の土浦城主として独立し、大河内右京大夫(うきょうたいふ)家を興されたとき、我が家の初代幸政という人が付け家老として派遣され、そのまま右京大夫家の家臣となった。(ちなみに私の名前は父の「克」に初代幸政の「政」を頂いて「克政」としたそうである)。
高崎との関係は、我が家の二代目幸継が、右京大夫家の二代目輝貞公が栃木県の壬生を経て高崎城主に転封されたのに付いてきたことに始まる。
よく「堤さんとは、世が世ならば一緒に座れない」などと言われるが、これは我が家が家老を務めたからなのだろう。しかし「蛙の子は蛙」でも、家老の子は家老になれるわけではない。それなりの能力や相応しい年齢、他に就任している家老とのバランスなど、条件が合わなければ就任できない。我が家でも、親子が続けて家老になったのは六代と七代、で二代から五代は家老ではない。ただ城代、年寄、番頭などの重要職は務めている。
家老の子だからといって家老になれないが、そうは言っても家老になれる家はだいたい決まっていた。複数の人が家老を務めた家に、浅井、大河内、神保、菅谷、田中、長坂、深井、深尾、宮部家がある。そんなことから狂歌に「長坂を 登りつめれば堤あり 浅井深井で越すに越されず」と詠われている。表面的には「長い坂を登りきったら堤があり川で浅かったり深かったりなかなか越せない」ということだが、「長坂家を超えても堤家があるし、浅井家や深井家もあるから出世できない」と封建制を揶揄している一首といえる。この狂歌を亡父が山本聿水先生に書いていただき額装にし飾っている。