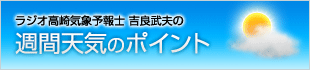ちょんまげ時代の高崎
第五話 中央政争終焉の地

安藤氏時代の最大の出来事はなんと言っても「駿河大納言事件」。
駿河大納言とは徳川忠長卿のことで、二代将軍秀忠の次男。甲斐、駿河、遠江五十五万石という御三家並の大大名で、従二位権大納言に任じられていたので駿河大納言と呼ばれた。家康は何人かの子供を失い、また子供によっては冷遇したりしたが、可愛がった末子たちは尾張六十二万石、紀伊五十五万石、水戸三十五万石の御三家とした。秀忠としても、三代将軍の長男家光の八百万石に対し、次男の忠長卿に五十五万石の所領を与えるのも当然と言えば当然なのだろう。
しかし、政権不安定を恐れた兄とその幕僚たちは忠長の所在が目障りだった。いろいろ画策したあげく忠長卿を高崎に蟄居させ、可愛がっていた母と秀忠が死ぬと城主安藤重長に切腹せることを命じ、察した忠長卿は高崎城にて自害された。
このやり方は、父秀忠が高田六十万石の城主であった弟の松平忠輝を改易したように、自分の案泰のために抹殺したとしか思えない。
このような悲劇が起こった遠因は、両親が長男より次男を溺愛したからと伝えられている。つまり、秀忠夫人は、成長遅れの長男竹千代(家光)より、聡明な次男の国松(忠長)を可愛がり、その愛が昴じて国松を将軍にさせたくなってきた。すると妻に頭が上がらなかった将軍秀忠もその気になり、国松の取巻きの幕閣も自分たちの出世のためもあったのであろう「次期将軍は国松君を」と考えるようになった。当然長兄の家臣たちは不安になり、まだ大御所として睨みを利かせていた家康に泣きついて、「長男竹千代が後継者である」と決めてもらった。
この結果、中央権力者の坐を争った方の終焉の地が高崎であったことは、勝者の歴史の下で忘れられてしまう。