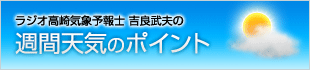農業・観光との連携がカギに
(2008年12月17日)
 高崎市の商工団体がパネラーに
高崎市の商工団体がパネラーに
「新高崎市の商工業を考える」シンポジウム
高崎経済大学市民公開シンポジウム「新高崎市の商工業を考える」が十二月三日に高崎市総合福祉センターで行われた。
パネリストに高崎商工会議所・原浩一郎会頭。高崎市箕郷商工会・高橋基治会長。高崎市榛名商工会・中島正三会長。高崎市倉渕商工会・追川清会長。高崎市新町商工会・相原武会長。高崎市群馬商工会・後閑泰司副会長。高崎市・座間愛知副市長。各地域の商工代表者が一堂に介して意見交換をするのは初めて。各地域の問題点が指摘され、これからの本市の商工業振興について議論された。新高崎市の活性化には農業、観光資源との連携の必要性が強調された。
高経大・戸所隆教授、村山元展教授、佐々木茂教授、河藤佳彦准教授、同大附属産業研究所・西野寿章所長から地域課題について提言された。発言要旨は次の通り。
高崎商工会議所・原浩一郎会頭「新高崎市は烏川流域の合併で、一体的な地域として連携の重要性が高まっている。高崎市は2新幹線6在来線の交通の要衝。金沢市との交流では大きく評価されていることを感じた。高崎市は中心市街地活性化計画に着手し国の財政支援も受ける。商工会議所も新都市創造推進委員会を設置する。農業では小麦、畜産、梅など全国有数の産地であり流通消費をつなぐのも商工会議所の重要な仕事だ」。
箕郷商工会・高橋基治会長「箕郷は県道8路線が通り、便利だが狭隘。歩道、拡幅などの整備が必要だ。吉岡町は上毛大橋の開通や産業道路の整備で発展した。箕郷地域の振興に道路整備が必要だ。フルーツライン二期工事、西毛広域幹線計画を進めてほしい。箕郷梅林、芝桜公園の集客を商工業振興につなげたい」。
榛名商工会・中島正三会長「榛名は観光ゾーンに位置づけられている。人口は新幹線を境に上は減少、下は増加している。榛名湖、榛名神社周辺では蕎麦打ちなどお店に人を呼び込むように努力している。406号沿いの郊外店が出店し、商店街はシャッター通りだ。店を継いでもお金にならず、後継者がいなくて廃業している」。
倉渕商工会・追川清会長「倉渕の人口は五十年で8千4百人から4774人、半分になった。高齢化し、林業で生活できず山林は荒れイノシシ、サル、クマのによる被害も出ている。また休耕農地が増えている。地元の商店は売り上げが減少し、品数を減らし悪循環で衰退に歯止めはかからない。土木などでは合併で高崎市の入札資格に満たなくなり、村の時には受注できた仕事が、入札もできなくなっている。こんなはずではなかったと厳しい状況だ。地域の商工業振興にいかに取り組んでいくか大きな問題だ。会員の声を聞いて、振興に役立てていきたい」。
新町商工会・相原武会長「合併するまで高崎地域との交流はなかった。新町は人口密度が高いまちで高崎線、国道十七号がまちのど真ん中を通っている。自衛隊、カネボウを誘致し大きな敷地を占めている。消費者は郊外店に流れ、商店街からお客が遠ざかっているが、まちづくり団体か活躍している。まとまりがよく協力してくれる人がたくさんいて頼もしい。行事では毎年お客様が増えており、高崎市にPRしてもらっている効果が出ている。地域は地域で守っていくことが大事だと思う」。
群馬商工会・後閑泰司副会長「群馬地域は高渋バイパスなど交通アクセスが良く、発展してきた。イオンモールのオープン、新たな人口流入も多く地域の活力を現している。群馬地区は商店街を形成していない。イオン開店の前後、会員にアンケート調査したが著しい客離れはなく、激しい衰退はない。商店、スーパーもイオンと住み分けている。イオンとイオン出店者も商工会に加入する方向だ。工業地域からベッドタウン化し、新旧住民、高齢者、若い世代との交流が重要。優良農地も多い」。
戸所隆教授「新高崎市は四倍の面積になった。地域の性格も違い多様だ。高質な都心部をつくり、各地域では利便性を高めていく必要がある。榛名の社家町では客の3分の2は県外から。店が早く閉まってという要望があった。高崎駅は群馬のゲートウェイで、どこへどう行くか情報発信が不十分。地域の日常は外から来た人にとって非日常であり、いかに見せるか、よそから来た人の目線で案内されていない」。
佐々木茂教授「顧客満足度を意識している企業は業績が良い傾向にある。企業のニーズでは大学には新商品開発やマーケティング、商工会議所にはマッチングへの期待が高い。高崎は地域力のPRが弱い。高崎に来れば何が作れるのか知ってもらうために産業マップづくりに取り組んでいる」。
河藤佳彦准教授「高崎市の工業は食料品、化学、金属、電気が特徴だ。大正期の工業出荷は県下最高で、製粉や板紙など農商工の取り組みが古くから行われていた。既存産業の集積、高崎の優位性を活用し、商工業連携や地元産業のブランド化をはかっていくことが必要」。
村山元展教授「高崎市農業振興計画は地域内自給を高めることにポイントを置いている。高崎市は合併で農村と都市が一体になり、生産と消費が一体化できるのがメリットだ。農業生産ばかりでなく消費者にどう買ってもらうか。消費の改善、販売加工の支援を行う。食をポイントにして新しい産業を創造できる」。
高崎市・座間愛知副市長「合併により農業出荷は五倍になり、農業が一番ドラスティックに変化した。旧町村の商業と高崎駅前の商業のあり方は違い、ぐるりんの見直しで各地域の利便性を高めていく。高崎の立地性は優れ、工業団地に在庫が無く、スマートIC周辺に工業団地をつくっていくことも考えられる。商工会議所、商工会の交流連携で新しいものが生まれる」。
西野寿章所長「元気なまち高崎づくりがシンポジウムのねらい。大学も地域振興に積極的に取り組んでいく。観光は神社仏閣やきれいな景色だけでなく、地域の取り組みを見に来るのも観光の一つ。地域の特色ある取り組みに期待し、大学もお手伝いをしたい」。