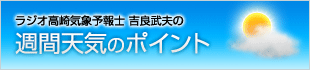高崎産農産物拡大で食料自給圏の形成を
(2008年11月17日)
新高崎市の豊かな農山村資源を活かし、各地域の一体的な農業の振興を図るため、市は農業振興計画策定に取り組み、このほど原案をまとめた。策定委員会での作業と平行して市民懇談会、農業者懇談会を開催し、生産者と消費者双方の視点から課題をとらえた。
高崎市農業振興計画の計画期間は二十一年度から十年間。本市農業の将来像に「多様な農業による食料自給圏の形成」を掲げた。市内の多様な農畜産物、加工により、市民の食料をまかない、高崎地域の食料自給率を高めていく。
高崎市の試算では、高崎市民の農産物消費を市の生産量でまかなえる農産物可能供給率は36%で、同計画の実施によって平成二十四年には40%をめざす。市民一人一日当たりの米の消費量は220グラム。生産量は66グラムで可能供給率は30%。小麦32%、野菜23%、肉24%、果物19%。100%を超えているのは牛乳の107%。
安全安心な地場農産物を求める市民ニーズに応え、農畜産物の生産拡大、流通消費の拡大、農山村環境の魅力拡大をはかる。広域的な販売・交流を進め、自然豊かな農山村環境を楽しむ暮らしを、農業者、市民、行政が協働で推進し、高崎市ならではの持続的な農業を創造する。
重点施策では、担い手の育成や人手不足解消のための援農人材バンクの設立。市民の関心の高い環境保全型農業の普及と特別栽培農産物の拡大。学校給食における地場産農産物の使用を現在の33%から平成二十四年度35%以上に増加させる。中学生の職場体験ヤルベンチャーでの農家体験実施を現在の7校から9校に拡大する。
地域別計画では、高崎、新町地域では都市農業の推進。倉渕地域では、山間地域の特性を生かした農業活性化。箕郷、榛名地区では果樹を生かし、観光と連携した農業の展開。群馬地域では露地野菜を生かした農業を推進する。市民、住民による地域づくりでは、農家と住民協働のコミュニティ農園、高齢農業者と果樹農家の連携による共同直売、棚田をめぐる健康散策路づくりなどを例示している。
各地域にはブランド化した農産物があり、高崎市産としての販売促進が重要となっている。高崎ブランドの構築と戦略的なPRを展開し、イメージアップと販路拡大をめざしていく。十二月にパブリックコメントを実施し、三月までに最終計画案を策定する。