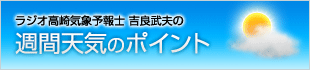上中居から破鏡出土/関東では3例目
(2008年10月24日)
 上中居遺跡から発掘された破鏡
上中居遺跡から発掘された破鏡
高崎市教育委員会が調査している上中居遺跡から青銅鏡の破片が出土した。東口線と環状線の交差点東南付近でみつかった。出土品は「破鏡」と呼ばれ、東日本での発見はまれだという。市教委の調べでは、全国では200例あるが、関東では3例目。多くは九州から出土している。
上中居土地区画整理事業に伴う調査で、古墳時代前期から中期(約1600〜1700年前)と考えられる幅約70cmの溝の中から勾玉、管玉とともに発見された。市教委は、鏡の本来の直系を12・8cmと推測している。鏡は後漢時代(二世紀頃)に中国で製作された後漢鏡で、三国志に描かれた時代。日本では邪馬台国の時代(弥生後期)にあたる。
破鏡は、完全な鏡を意図的に割り、破片を磨いたり摩耗して使われた。小さな穴があいていることもあり、ペンダントのように利用されていたとも考えられる。製作された時期と廃棄された時期に100年から200年の開きがあり、長期間使用されていた。鏡は墓に埋葬されることが多いが、破鏡は住居跡や溝など墓以外の場所から出土することが多い。弥生時代中期後半から後期の西日本、特に九州北部での出土が多く関東地方ではまれ。古墳時代前期には廃れている。
西日本で流行した破鏡が高崎で発見されたことは、光の象徴となる鏡を用いた祭祀が当地まで及んでいたことを示している。また居住域から離れた溝の中から出土していることから、この場所で水に関わる祭祀が行われていたと推定される。
観音塚考古資料館で10月25日から公開される。