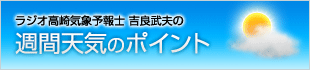「音楽センターは市民文化の象徴」
(2008年10月16日)
 音楽センターと高崎の市民文化について鼎談
音楽センターと高崎の市民文化について鼎談
高崎JC主催で市政フォーラム
高崎青年会議所主催の市政フォーラム「音楽センターから考えよう」が十四日に群馬音楽センターで開催された。群馬音楽センターの問題を市民で考えようと呼びかけ、青年会議所メンバーによる基調報告と有識者の対談が行われた。
群馬音楽センターは、昭和三十六年に建設費の三分の一を市民の浄財により建設され、群馬交響楽団とともに、高崎市民の文化活動の象徴となってきた。フォーラムでは高崎青年会議所の善如寺信哉さん、佐藤泰然さんが基調報告し、松沢睦さん、水上勝之さん、石沢久夫さん、風岡優さん、平井誠一さん、根岸良司さん、堤志行さんの意見を映像で紹介。歴史的な意義、建築物としての芸術性、コンクリートの劣化などの問題、演奏上の音響、興行時の不具合など、音楽センターについての様々な意見を聞くことができた。
音楽センターは高崎の都市計画の柱として建築され、日本近代建築の傑作であること。大編成オーケストラの編成には不向きであり、新たに二千席を持つホールや群響専用のホールを建設すべきなどの提案があった。音楽センターを使い続けるための補修に20億円、新たなホール建設には100億円が必要とされる。センターの解体には5億円の費用がかかることが示された。
対談では、高崎経済大学副学長・大宮登教授、NPOぐんま・熊倉浩靖代表、群馬建築士会高崎支部・信沢卓支部長が音楽センターと高崎のまちづくりについて意見交換した。
熊倉さんは「井上房一郎氏とレーモンドは日本文化への同じ思想を持っていた。戦後の焼け跡から、音楽をきっかけに市民を世界につなげようと思いが音楽センターになった」。
信沢さんは「レーモンドは戦後日本のめざす建築を示した。レーモンド建築で音楽センターが一番大きい。我々は芸術品の中で催し物をやっている。建築家の一人として大事に使っていければと考えている」。
大宮さんは「都市の視点から音楽センターを見れば、まちの拠点、交流の場として高崎の文化の質を現している。市民力の象徴、文化の発信地として考えるべきだ」と述べた。音楽センター、新芸術ホール、市民活動・都市政策の問題を分け、それぞれ整理していくことが重要とされた。
また、信沢さんは音楽センターの建設に従事した人が来場していることを紹介し、「市民がお金を出し、汗を流して建てたことが大切だ。音楽センターの折板構造は地震に強い。八十年は使える。改修で技術的に解決できる」と話した。
大宮さんは「市民の愛着は簡単に生まれるものではない。市民が愛着を持ち共有できるものが多いほど市民の力が発揮できる。高崎の財産はたくさんあり、守り育て、戦略的な展開が必要だ。みんなで徹底的に話しあっていこう」。
熊倉さんは「戦後高崎の文化がここから生まれた。原点に戻って考えよう。音楽センターを使い続けながら、世界に誇れるもう一つのホールを作れるよう経済的にも精神的にも強い市民になることが必要だ」とまとめた。
群響主席チェリストレオニード・グルチンさんの演奏も行われ、来場者の思いを深めた。高崎青年会議所の小沢健一理事長は「今日は第一歩。市民一人ひとりが市政に参加し、住民参加の高崎のまちづくりを進めよう」とあいさつした。