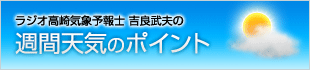新編倉渕村誌資料編を発刊
(2008年10月2日)

新編倉渕村誌資料編
倉渕村誌刊行委員会(市川平治委員長)は、新編倉渕村誌資料編第1巻、第2巻をこのほど刊行した。
倉渕村誌は、合併前の平成十五年に着手し、新高崎市が編さん事業を引き継いだ。全四巻の構成で、昨年に第三巻「民俗編・自然編」を刊行している。資料編の第一巻は「原始・古代、中世、近世」、第二巻は「近代、現代」。村誌編さん委員会は、今年度末までに最終巻となる「通史編」をまとめる予定。
倉渕村は、榛名山と川浦山の間を流れる烏川と支流域で、榛名山西麓を中心に古くから開発されてきた。平安時代以降、榛名信仰の重要な地域でもあり、草津や善光寺への街道として宿場も形成された。源頼朝が通行した伝承も残っている。戦国の世では、武田氏の上州侵攻にも使われ、箕輪城の長野氏と信濃、西吾妻をめぐる戦略的にも重要な地域となっていた。近世では、信州と西上州の物資輸送に大きな役割を果たしている。
近現代では、旧倉田村・烏渕村の資料とともに、地域の協力や地元編さん委員の研究が大きな成果をおさめた。倉渕地域の特色は、85・5%が山林であり、高崎市の水源涵養林、クラインガルデン、横須賀市との交流、はまゆう山荘の建設なども取り上げられている。編さん委員会近代・現代部会の森田秀策部会長は「過疎化・少子化・高齢化の実態が浮きぼりとなり、地域活力の低下が課題。厳しい客観情勢の中で地区の振興、活性化をはかるには、地域の資源や人材を生かして活動を起こすことが望まれ、地区内で新しい動きも始まっている」と指摘している。
小栗上野介公については章を設けて詳述し、日記や関連航海日誌、処刑の記録などを採録した。近現代では人物編として、豊田勇、豊田一男、宮下秀洌、名誉村民濱名一雄ら政財界、芸術文化で著名な十一人を取り上げている。
頒価は三千五百円。高崎市役所市民サービスセンター、倉渕支所で販売。問い合わせは倉渕支所378・3111。