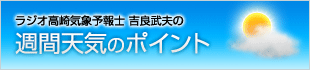AEDで蘇生/6カ月で40件の使用
(2008年9月9日)
 設置が進み救急救命に役立っているAED
設置が進み救急救命に役立っているAED
市内の公共施設などで、AED(自動体外式除細動器)による応急処置が、今年3月から8月までに40件になっていることが、高崎市議会で報告された。六日の長壁真樹議員の一般質問に答えた。AEDは市有施設、小中学校など212カ所に設置されている。民間でもスポーツ施設や人が集まる施設で設置が進んでいる。
事例では、高崎市役所で、来庁者が倒れて心肺停止となったが、職員がAEDと応急救命処置を行って蘇生し、消防局救急隊員に引き継ぎ、一命をとりとめた。この患者は45日後に退院し、現在後遺症もないという。
浜尻小学校学童クラブでは、保護者が倒れて心肺停止となり、学校保健士がAEDで処置を行い、蘇生したという。
高崎市消防局は、通報、応急処置、救急隊の処置、搬送が迅速に行われることが重要だと強調している。消防局では、救急救命講習を実施し、平成19年度は市民など9896人が受講している。多くの市民が受講するよう呼びかけ、救命率を向上させたいと取り組んでいる。消防局が主催する講習会のほか、企業や団体で人数がまとまれば、出張講座にも応じている。
学校開放でスポーツ活動などで市民が校庭や体育館を使用する機会も多い。休日や夜間など学校職員の不在時に、利用者が心肺停止に陥るケースも考えられる。市教委では、そうした緊急時は、AED表示された窓ガラスを割って校内に入り、AEDを使用できるものとし、市内各校に伝えているという。
AEDは、除細動が必要か機械が判断し、手順を音声で指示。簡単に処置が行えるようになっている。平成16年から国が非医療従事者も使用が認める方向を出し、市内でも設置が進んできた。
119番通報から救急車の到着までの全国平均時間は6分30秒。病人が倒れてから除細動開始まで十分以上かかることになる。処置が一分遅れるごとに生存率は10%ずつ下がると言われ、救急救命では、一刻も早い処置が必要とされている。