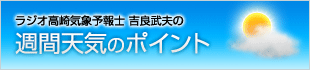児童虐待で十八機関が連携
(2008年8月1日)
 代表者会議は児童虐待に関する環境整備をはかる
代表者会議は児童虐待に関する環境整備をはかる
高崎市は、虐待を受けている子どもなど要保護児童の早期発見や適切な保護をはかるため、関係機関が連携する「高崎市こどもを守る地域協議会(湯浅僖章会長・委員二十三人)」を四月に発足させた。第一回代表者会議が七月二十五日に開かれた。
協議会は児童福祉法に基づく組織で、児童相談所、保育所園、幼稚園、小中養護学校、警察、家庭裁判所、医師会、歯科医師会、社会福祉協議会など十八機関の連携により、児童虐待防止対策などの取り組みの強化をはかる。同法の改正により、これまでの児童虐待防止ネットワーク連絡協議会が発展的に移行した。
平成十七年以降、県の児童相談所だけでなく市町村も相談窓口になり、十八年から二十四時間体制で相談を受け付けている。協議会の設置により、さらに体制が強化された。代表者会議、実務者会議、個別ケース会議で構成され、構成各機関が情報を共有し、要保護児童へのより良い支援を行う。委員には守秘義務があり、プライバシーの保護も強化されている。
児童虐待の早期発見と保護のためには、市民の協力と関係機関の連絡が不可欠だ。子育てに悩み相談できずに精神的に追い込まれ、深刻化するケースもある。身体的な暴力だけでなく、育児放棄や精神的な苦痛を与えるなど、問題は多様だ。
平成十九年度は相談総数161件のうち67件の児童虐待があった。身体的虐待が40件、性的虐待4件、心理的虐待11件、ネグレクト(保護育児の怠慢や放棄)12件。虐待者は実父23件、実母36件。子どもの年齢は二歳以下16件、未就学児26件、小学生21件。
通告や相談を受けると、調査、安全確認、緊急性の判断が行われる。関係機関が連携し、総合的な支援、援助が行われる。必要に応じて、児童を親から保護する。<
市民からの通告では、近所で毎晩、親の叱責で子どもが泣き叫んでいる、子どもを学校に行かせていないなどがあった。医師が診察の際に、不自然な傷やアザなど子ども達の異常に気付く。保育士の観察で虐待が発見され、保護者に直接言えないため、市に相談するなどの事例もある。同協議会の活動によって、関係機関が意識を共有する意義は大きい。
子どもの目の前での家庭内暴力も、児童に精神的苦痛を与えるため、虐待に含まれており、相談範囲が広がっている。高崎市では「大事に至る前に対処することが重要。市役所は市民に身近で相談しやすい。市全体で子ども達を守りたい」と話している。窓口は高崎市こども家庭課℡321・1315。相談専用電話 TEL: 321・1318。