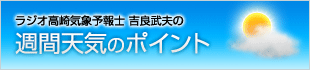准教授に停職6カ月の裁決
(2008年7月17日)
懲戒免職取り消しの申し立てに公平委員会が判断
自殺した高経大学生へのハラスメント(いやがらせ等)で懲戒免職になっていた同大准教授が、高崎市等公平委員会に処分取り消しを申し出ていた件で、同委員会の裁決(写し)が平成20年6月25日付で高経大に送付された。
裁決内容について、大学事務局が、16日の高崎市議会教育福祉常任委員会に報告した。
平成19年1月に経済学部2年生の女子学生が自殺し、その原因が准教授の理不尽で教育的配慮を欠いた留年通告にあった。演習指導上において、全体の奉仕者としてふさわしくない数々の行為があり、公務員の信用を失墜させたとし、大学は平成19年4月9日に准教授を懲戒免職処分した。准教授は、これを不服として高崎市等公平委員会に処分取り消しを申し出ていた。
公平委員会の採決により、懲戒免職は、停職6カ月の処分に修正される。懲戒免職処分された平成19年4月9日から6カ月間が停職期間となり、19年10月10日から准教授は、大学に復職したものとして事務手続きされる。同日以降の給与も規定に従って支給される
裁決は、大学が行った懲戒免職を軽減するかたちとなったが、6カ月の停職は、現実的には最も重い処分と考えられる。学生に対するハラスメントを認定し、大学の行った決定の妥当性を示した一方、公平委員会は自殺との関連性について判断を避けた。
公平委員会の裁決が決定した後、准教授は大学に出勤しているという。懲戒免職の処分を受けていたため、平成20年度のカリキュラムには准教授の担当科目は無い。
准教授は、前任の大学を学生に対するハラスメントで懲戒免職処分を受けており、今回の処分は二度目。高経大が准教授を採用した当時は、こうした処分歴をチェックしていなかったという。
平成18年8月から11月にかけて学生の自殺が三件連続し、大学では、学生相談などを強化。対人関係、健康問題、メンタル面など学生の諸問題を把握するため、同年に学生環境検討委員会を設置し、20年度は同委員会を常設化した。また学生相談連絡会議を毎月一回開催し、学生から寄せられる相談の内容や長期欠席など気がかりな学生の情報を学生部やカウンセラーで共有している。
本件に直接関係するハラスメント防止対策では、セクシャルハラスメントだけでなく、アカデミック・ハラスメント、パワーハラスメントなどを含めた対策委員会と相談室を平成19年度に設置している。
大学では、今回の公平委員会の裁決を真摯に受け止め、これまでに行ってきた再発防止のための改革を進めていく。