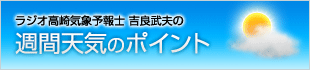高崎の都市戦略/第五次総合計画の初年度
(2008年1月10日)
高崎市の初代矢島八郎市長は、高崎市の創始にあたって市是、つまり施策目標を制定して取り組んだという。その原動力は、当時の産業界や市民の熱意にあった。
市是の大綱は二期に分けられ、第一期が水道敷設、教育設備の完成、道路改修、商工業の発達、市財源の確保、公園地の完成。第二期が下水道の完成、市の区域拡張、市区の改正、商工学校の設立となっている。この中には、高崎市が全国の先例として取り組んだ事業もあるが、上下水道、教育、商工業、道路交通、財政など、行政課題は百年前の矢島市長が掲げたものは、現在においても基盤事業として少しも変わっていない。中山道が高速道となり、上野高崎間の鉄道が新幹線となり、東西南北へ伸びる高崎市の都市力は、先人の叡智と労苦によって築かれたのだと、あらためて感じさせる。
「交流と創造〜輝く高崎」を掲げた高崎市第五次総合計画に、「将来の高崎は、群馬県のみならず北関東・信越地域を代表する拠点都市として東京と日本海を結ぶ政令指定都市をめざす」とうたわれたことは、特筆すべきだろう。
合併により人口三十五万人となり、高崎市はこれから中核市に移行する。政令指定都市(政令市)は人口五十万人以上で、札幌、仙台、新潟、名古屋、京都、大阪、広島、福岡などの大都市だ。政令市には市民生活に関わりの深い権限や財源が都道府県から移譲され、都市課題を自ら解決していく責務が大きくなる。
群馬県内の都市人口で言えば、一足先に中核市に移行する予定の前橋と合併すれば人口六十六万の県央都市ができ、政令市としての要件を満たすということも語られる。群馬県が北関東あるいは甲信越の中で力を発揮し、また将来の道州制導入をみすえた時、群馬県内に政令市級の都市が必要になるだろうとも言われている。松浦市長は、中核市移行後の高崎市の将来像として、政令市を視野に入れるべきだと、これまでも繰り返し発言してきている。
第五次総合計画は、倉渕、榛名、箕郷、群馬、新町の合併によって誕生した現在の高崎市域のまちづくり計画であって、もちろん新たな合併は計画の枠組みには含まれていない。高崎市が政令市をめざすという文脈には、将来の合併によるものではなく、今の高崎市が発展する線上にあるという意志が感じられる。
人口減少社会にあって、人口は政令市や力のある中核市へと集中する二極化傾向にある。高崎市は、地方都市の中でも人口が順調に増加している数少ない都市の一つだが、現在の高崎市の人口増加率で、三十五万人が五十万人に達するのは気の遠くなる話でもある。人口五十万人は、確かに政令市の要件であるが、むしろ政令市に並びうる都市力が、ここに至って見えてきた、市民福祉の向上、福祉・教育の充実、経済・文化活動を担う市民力、行政能力を問い続けるという決意に他ならない。そして高崎市が北関東、甲信越、北陸地域の中で担うべき役割が見えてきたという確信でもあろう。
第五次総合計画では、「市民がまちづくりの中心的な役割を担ってきたのが高崎ならではの伝統と精神」と位置づけられている。計画初年度となる二十年は、この伝統の上に立ち、高崎市が次ぎのステップに踏み出す基点の年になるだろう。