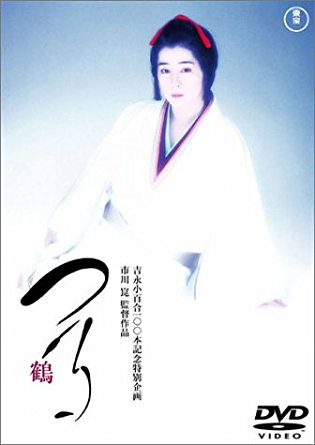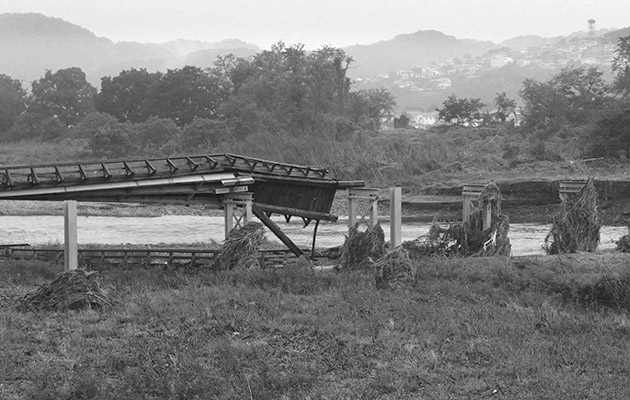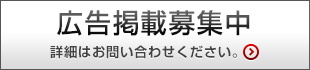古典花木散歩
12 をみなへし その3
吉永哲郎
平安王朝時代の女郎花は、単に美しい女性というだけでなく、男好きのするあだっぽい女性、男とすぐに一夜の宿をかす女を連想し、貴族たちは歌に詠み込んでいました。前回紹介した「蜻蛉」巻の薫君の歌の口語訳から、「女郎花」の意味を考えてみます。薫君の歌「女郎花の咲き乱れている野辺のような、この華やかな女房が集うておられるところに立ち入ったとしても、露に濡れた移り気な男だなどという評判を、つゆ負わせることができましょうか。根っからの実直男の私ですのに。」に、弁のおもとは「花と言えば女郎花なんて名前からして移り気な感じですが、だからといってどんな露にも簡単に靡き乱れるのでしょうか…、女郎花にも矜持がございますほどに、そう誰にでも靡きはいたしません。」と返します。多くの美しい女性の中にいても、わたしは浮名を負わせないと実直ぶりを示す薫君、弁のおもとは「女郎花の名は移り気のようですが、女郎花ほどの露にでも濡れて乱れたりしますか…、」と切り返しています。さらに、弁のおもとは、「旅寝してなほこころみよ女郎花さかりの色にもうつりうつらず」と薫君にせまります、薫君は 「宿かさばひと夜は寝なんおほかたの花にうつらぬ 心なりとも」と返します。弁のおもとが 「一夜泊って試してみて、女郎花の盛りの色にあなたの心が移らないかを…、」というのに薫君は「あなたが宿を貸してくれるなら一夜くらい泊めていただこうか。大抵の花には心を移さない私だが。」と答えます。王朝女郎花は奥が深いのです。
- [次回:13 ・うめ]
- [前回:11 をみなへし その2]