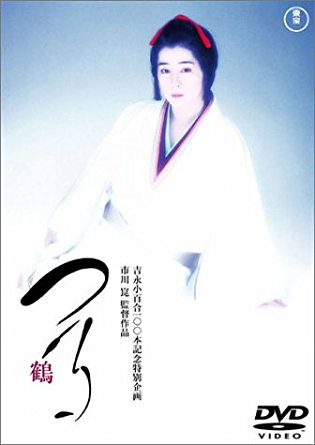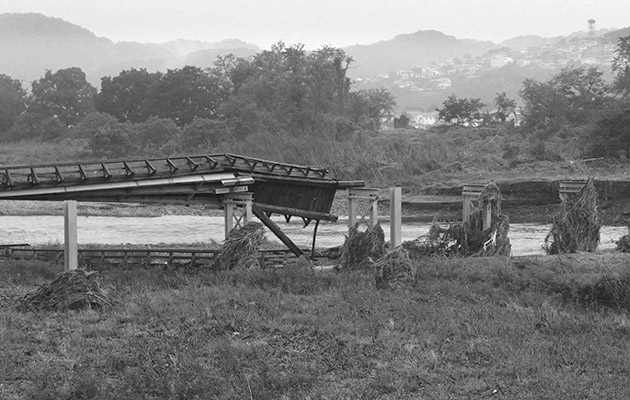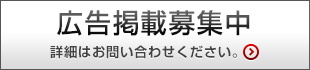古典花木散歩
10. をみなし
吉永哲郎
秋の到来を平安貴族藤原敏行は、「秋來(き)ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる」と、触覚によってとらえています。
それに対して万葉人の山上憶良は「秋の野に咲きたる花を指(および)折り数ふれば七種(ななくさ)の花」と詠み、次いで旋頭歌(577・577という歌体)「萩の花尾 花葛花瞿麦(くずはななでしこ)の花女郎花(をみなへし)また藤袴(ふじばかま)朝貌(あさかお)の花」と詠んでいます。
万葉人がこの七種で最も多く詠んでる花は「萩の花」で約140首、「梅」の歌が120余首、詠んでいます。こうして比較すると万葉人は視覚で季節の移ろいを感じとっています。
「をみなへし」は一般に「女郎花」と記しますが、万葉集には「佳人・美人・娘子・娘・姫」などの文字を当てています。万葉集には14首の「女郎花」の歌が詠まれていますが、「手に取れば袖さへにほふ女郎花この白露に散らまく惜しも」(手に取ると袖までも色づく女郎花が、この白露で散ってしまうのが、とても惜しい。)のように、花の可憐な姿から、女性を思う歌が多く、女郎花を美人と直接には表現するようになったのは、平安王朝以降のことで、『能因歌枕』に「をみなへし、女をたとへて詠むべし」とあることから、歌詠みの基本になったと思われます。
古今集掲載歌2首、紹介します。
名にめでて折れるばかりぞ女郎花われおちにきと人にかたるな
秋の野になまめきたてる女郎花あなかしがまし花もひととき
- [次回:11 をみなへし その2]
- [前回:9 ・朝顔 (その二)]