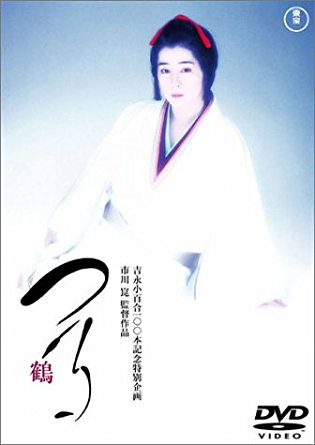銀幕から生まれた昭和の映画女優7
細身の体から溢れ出る情感漂う声色・歌う銀幕スター -浅丘 ルリ子-
志尾 睦子

日本の映画史において、初カラー作品は松竹映画の『カルメン故郷に帰る』(1951/木下恵介監督)であるが、当時を想像すると、何を自社のカラー第1作にするかは各映画会社にとって一大事だったにちがいない。
日活の初カラー作品は1955年の井上梅次監督作品『緑はるかに』である。この作品で主演銀幕デビューをはたしたのが浅丘ルリ子さんだ。科学者である父の研究秘密を盗もうとするスパイ団に、娘のルリコとその仲間達が立ち向かうという物語。読売新聞に連載されていた北条誠の小説の映画化だった。日活は映画製作にあたり、主人公ルリコ役を公募。当時都内の中学校に通っていた浅丘さんが応募し、見事3,000人の中からオーディションで選ばれた。小説の挿絵を書いていた中原淳一さんが、オーディションに現れた浅丘さんに吸い寄せられ、その場で彼女の長い髪を挿絵と同じくショートカットにしてしまったという逸話まである。その状態でのキャメラテストで満場一致となり、大役を射止めることとなったそうだ。
役名をそのまま芸名としてデビューした15歳の少女は、美少女として脚光を浴び、そのまま日活看板女優の道をひた走ることになった。小林旭、石原裕次郎といった日活スターの相手役として出演を重ねた。『丘は花ざかり』('63/堀池清監督)、『夕日の丘』('64/松尾昭典監督)など主題歌を手がけるものも増え、歌う銀幕スターとしての一面も見せた。
二十歳をすぎると日活スター映画を彩る美しい女優という位置付けから、演技派としても頭角を表していく。それに一役買ったのが蔵原惟繕監督で、『憎いあンちくしょう』(1962)、『何か面白いことないか』('63)、『夜明けのうた』('65)の典子三部作、そして『執炎』('64)、『愛の渇き』('67)といった作品で、浅丘ルリ子の新たな魅力を引き出した。
日活との専属契約を解消したのち、石原プロダクションに移籍。そこでリリースした「愛の化石」は50万枚を超えるヒット曲となった。台詞の多い楽曲スタイルは浅丘ルリ子の豊かな情感漂う声色あってのものだったに違いない。
その後も、映画にテレビにと出演作は事欠かない。寅さんシリーズでの旅回りのキャバレー歌手・リリーは、人気が高じてシリーズ最多となる4度の出演ともなった。
年を重ねるごとに違った役柄で新たな魅力を発信し続ける銀幕女優のお一人である。