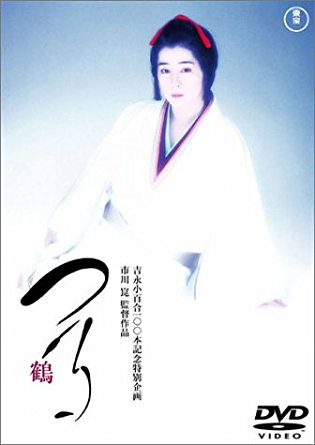私のブックレビュー11
『どろぼうのどろぼん』
志尾睦子
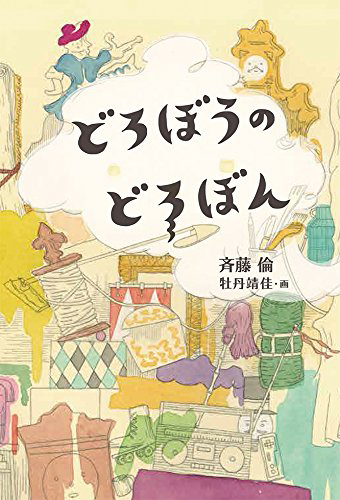
斉藤 倫著
福音館書店
かつてはみんなどろぼんだった(カモシレナイ)
本が読みたいけれど小難しいものはちょっとしんどいな、というときにこそおすすめなのが児童文学です。子どもでも読みやすく、わかりやすい表現で綴られた物語には、さまざまな気づきが隠れていて、硬くなった頭がいつもほぐれていく気がするからです。本作は、最近読んだ児童文学の中でも飛び抜けて面白く、加えて涙腺が緩んでしまう逸品でした。
主人公はどろぼん、ではなく刑事のチボリさんです。とある事件を調べていたチボリさんは、急な雨降りに見舞われ、雨宿りのために飛び込んだ軒先で一人の男に遭遇します。その男は、どろぼうのどろぼんだと名乗りました。どろぼうしたところを見たわけではないけれど、刑事だから、どろぼうと名乗られたら調べないわけにはいかないチボリさんは、どろぼんの取り調べを開始します。
「背はのっぽというには低すぎるけど、ちびというには高すぎる。体格は少しがっしりしているように見えたが、来ているシャツによっては、ほっそりして見える」「いつもなにかと、なにかの、中間にいる」
ようなどっちつかずの人物どろぼんは、人の記憶からすぐに消えてしまうようです。だからか、自己申告では千回どろぼうしたそうですが、一度も捕まったことがないと言います。また、どろぼんがどろぼうしたものたちが、盗まれた人にさえ忘れ去られていたものだった、というのも理由の一つのようです。どういうことかといえば、ここから連れ出してほしいと叫ぶモノの声がどろぼんには聞こえてくるのです。彼はその声に導かれ、知らない家に入り、その声の主を連れて出てくる。誰にも必要とされないモノたちをどろぼうし、誰か必要に思ってくれる人に受け渡す、それがどろぼんのやり方でした。取り調べで語られる様々などろぼんの前科には、どれも切ないエピソードがついて回りますが、持ち主に忘れられたモノたちを救い出すことでその持ち主の人生を少しだけ変えたり、関わる周囲の人の心を少しだけ軽くしたりします。そうしてどろぼうを繰り返してきたどろぼんでしたが、ある出来事を境にして少しずつ、モノの声を聴く能力が薄れていきます。その理由に深く大きく頷いてしまいました。
一つ一つのエピソードに、ああそういう見方があったのか、と驚く瞬間が散らばっていて飽きることがありません。いつも見ている角度と真逆からものごとを捉えてみることの大事さ。それに改めて気付かされる時間は至福でした。
- [次回:『文房具56話』 ]
- [前回:『わからない音楽なんてない! 子どものためのコンサートを考える』]