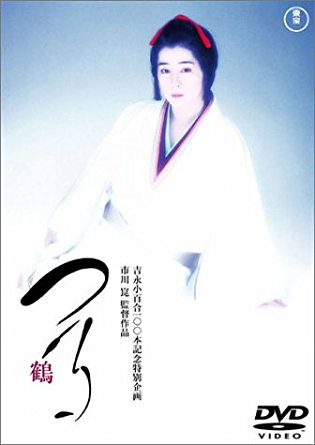映画の街高崎-高崎映画祭30周年
(2016年02月25日)
毎年3月末から始まる高崎映画祭は、高崎の春の風物詩で、多くのファンが開幕を待ちこがれている。高崎は「音楽の街」とともに「映画の街」と呼ばれるようになった。「映画」が高崎の特徴的な都市文化にまで育ったのは、今年30回を迎える高崎映画祭を中心に、揺るぎない信念とひたむきな情熱を持った市民がまちを突き動かし、共感と応援が続けられてきたからである。
第30回高崎映画祭では「映画の街高崎」を縦糸、「音楽の街高崎」を横糸に高崎の都市文化を織り上げるのも大きな見どころだ。
「商工たかさき」 2016/2号より
■「音楽の街」と「映画の街」が一つに
●高崎文化の源流に岸惠子さん
今年の高崎映画祭では第30回を記念する特別賞が、映画「ここに泉あり」(昭和30年2月封切り)にピアニスト役で主演した岸惠子さんに贈られる。
音楽によって戦後の復興をめざした群馬交響楽団は「音楽の街高崎」の象徴だ。そして楽団草創期の苦闘を描いた映画「ここに泉あり」は、全国に感動の渦を巻き起こし、群響発展や群馬音楽センターの建設など高崎の文化創造に大きな影響を与えた。「ここに泉あり」の撮影では俳優やスタッフが高崎に長期宿泊し、市内ロケでは、連日1千人の市民エキストラが動員されたが、これは映画などの撮影支援を行う、現在のフィルムコミッションの先駆けで、「映画の街高崎」の原点と言える。
「ここに泉あり」は、高崎を特徴づける二つの文化「音楽の街」と「映画の街」の源流となる作品であり、岸惠子さんの特別賞受賞は、全高崎市民が称賛するものとなるだろう。30回の節目に、高崎映画祭がこの映画の位置づけを新たにしてくれた。岸さん自身に、「ここに泉あり」や高崎、群馬でのロケについて語ってほしいという願いは大きく、岸さん来祭への期待がふくらむ。
また、第30回高崎映画祭では、今回初めて群響によるオープンニングコンサートが会期初日の3月26日(土)に群馬音楽センターで行われる。これも「音楽の街高崎」と「映画の街高崎」がコラボレーションする企画で、高崎を象徴するものとなる。第30回は、高崎の新たな都市文化を創造する意欲的な開催となりそうだ。
■映画文化を育てるクリエイティブな都市
●映画業界で評価される「映画の街」
高崎は、映画人から非常に高く評価されている都市である。まず高崎映画祭を長く市民が運営・支援し、映画に対して理解があり、とてもあたたかいまちであると言われる。ミニシアターの常設映画館「シネマテークたかさき」では、シネコンとは異なった商業的には弱い映画を上映し、高崎映画祭と合わせて、「高崎市民は映画というものが良くわかっている、見る目が肥えている」と、日本の映画界で思われているようだ。
高崎市民が本当に映画をわかっているか、ということはさておき、シネマテークのように小さくて個性的な映画館は、東京都内が中心で、地方都市には数が少ない。まして30年前に高崎映画祭が始まった頃などは、大手映画会社の配給に乗らないたくさんの映画は、地方で上映されることは限られ、高崎映画祭は映画制作側にとっても、とても貴重な存在だった。高崎映画祭とも親しかった故・若松孝二監督は、「映画をいくら作ったってかける劇場がなければ始まらない」と発言していたが、高崎は多様な映画を上映する劇場なのだ。高崎映画祭やシネマテークが新たな映画ファンを創り、ファンを育ててきたことは大きな功績だ。
これに加えて、映画撮影を支援する「高崎フィルム・コミッション」は、とても面倒見がよく、高崎の街並みは昭和の懐かしい風景から現代のオフィス街、風光明媚な自然、特撮ヒーロー番組の秘密基地まで、実に様々なシーンが撮影される。海がないのに船上シーンを撮影したこともある。人口規模もあるので、大勢のエキストラが必要な場合も対応できる。高崎に来ればいい映画ができると評価が高い。
映画制作の現場に携わるフィルムコミッション、出来上がった映画を上映するシネマテーク、映画を評価し芸術性を高める高崎映画祭。映画に関わる全ての可能性を高崎は持っており、こうしたまちは他にはない。高崎映画祭を中心とした30年間の活動によって、高崎は「映画の街」になった。
●黄金時代を味わう昭和映画の殿堂
「映画の街高崎」の魅力を高め、映画の味わいを更に深めることになったのが、高崎電気館の復活だ。
高崎電気館は、高崎で初めての常設映画館として百年前の大正2年に開館し、市民に親しまれてきた。現建物は昭和41年に建てられたもので、平成13年に閉館した後も、所有者の広瀬公子さんが保存に努めてきたので、奇跡的に当時のままの姿を保ってきた。広瀬さんから土地・建物の寄贈を受け、高崎市は平成26年にまちなかの文化発信拠点「地域活性化センター」として復活させた。1階は交流施設、2階は広瀬さんの希望通りに映画館となっており、昭和映画の黄金時代を彷彿させる建物だ。
復活した電気館では、群馬交響楽団の草創期を描いた「ここに泉あり」を定期的に上映しているほか、これまで市川雷蔵、若尾文子の特集などを上映。電気館と昭和映画の魅力がしっかりわかっている心憎いセレクションで、今年1月は、昭和の正月の定番である寅さん映画を上映し、都内から寅さんファンのグループが、コスプレで来場するなどの評判となった。高崎の電気館は、ここでしか味わえない昭和映画の殿堂と言えるだろう。
●クリエイターがつながる都市
高崎に映画づくりの人々が集まり、映画を愛するファンが集まり、そのファンと交流し発信するために俳優や監督らが訪れ、その循環が深く大きくつながりあっている。この潮流の中心にいるのが、NPO法人たかさきコミュニティシネマ代表で高崎映画祭プロデューサーの志尾睦子さんとその右腕、たかさきコミュニティシネマが運営する「シネマテークたかさき」の支配人・小林栄子さんの名コンビだ。
昨年から、それまで高崎市役所が行っていたフィルムコミッションの仕事が、志尾さんが代表をつとめるNPOたかさきコミュニティシネマに委託され、また高崎電気館の映画館運営も志尾さんに任されるようになった。つまり高崎映画祭、フィルムコミッション、シネマテーク、高崎電気館という「映画の街高崎」の文化が、高崎映画祭を核に集約され、一本の大樹になったのだ。撮影現場に始まり、スクリーンでの上映、企画運営など映画に関わるクリエイターが高崎に集まってくる、映画の楽しさを求めて、ワクワクしながらファンが集まってくる。高崎はそうした映画の街なのだ。
映画で高崎の街をもっと面白くする。第30回高崎映画祭は、そのクランクインとなる映画祭だ。
●映画と高崎を愛する心の結晶
そもそも高崎映画祭の始まりは「見たい映画を見る」ために市民が手作りしたフェスティバルで、物好きの集団と思われていた。中心となった看板男、茂木正男さんが平成20年に他界し、志尾さんたちに未来が託された。高崎映画祭の揺るぎない信念が受け継がれ、映画とともに高崎をこよなく愛する気持ちが根底にある。
茂木さんのようなカリスマ的存在を失った時は心配が広がった。志尾さんも小林さんもおおらかな人がらのために素振りに現れないが、茂木さんを実質的に支えて過酷な映画祭ボランティアを長く経験してきた叩き上げで、単に茂木さんの遺産を引き継いだだけではなく、新たな魅力を創造する熱い意欲にあふれている。
高崎映画祭を立ち上げる時、茂木さんに協力を頼まれた多くの人たちは「俺には映画はわからん」と言いながら熱意に引き込まれた。「映画好きの茂木さんたちを、映画に関心が無い人たちが大勢で応援する仕組みができたから、高崎映画祭が続けてこられた」と当時を知る人は語る。高崎映画祭の応援者の中には、映画はわからないが、「高崎映画祭が好き」という人も数多い。
■映画のプロが交流する街
●創造を続けてきた独自の芸術性
高崎映画祭は、会期の2週間で60本から70本の映画を上映している。高崎映画祭の上映プログラムを見ると、「知らないタイトルがいっぱい」と感じるのが、多くの人の率直なところかもしれないが、映画ファンにとっては「見たい映画がいっぱい」なのだ。どちらかというと玄人好み、「プロの映画ファン」が集まる映画祭である。
全国一斉に公開されるロードショー作品に対し、高崎映画祭は地方で興行されにくい映画を中心に上映し、全国の映画ファンに注目された。金曜の夜から高崎に宿泊し、日曜の午後までたっぷりと高崎映画祭に浸って、帰って行くファンもいる。
「茂木さんは隠れた名画ばかり選んでくる」と言われながらも、高崎映画祭で上映される作品の魅力はファンを広げた。確かにあまり知られていない作品もあるが、そうした作品が醍醐味となり映画ファンが集まってくる。上映作品や受賞者は、高崎映画祭ならではの切り口で丹念に選ばれ、映画ファンや映画業界に一目置かれている。30年間に高崎映画祭が注目した若手監督や新人俳優が大きな活躍を見せており、新たな才能を見出し、育てる役割も果たしている。
●映画界の巨匠が高崎を評価
高崎映画祭は、芯を持った映画祭としてファンや映画人に芸術性が評価されている。授賞式に出席するために、多忙な映画監督や俳優が、スケジュールを調整して高崎にやって来るのは、映画人が高崎映画祭を愛し、大切にしていることの現れである。どうしても出席できない時は、代理で更に大物が現れたり、受賞俳優のお祝いにその映画の監督が顔を出したりするなどのサプライズも、高崎映画祭ならではだろう。「高崎映画祭はあたたかくて楽しい。ぜひもう一度受賞して高崎に来たい」と授賞式で俳優や監督が口々にしている。
昨年の第29回では授賞式に登壇した大林宜彦監督が30分以上にわたって映画への思いを語っていった。高崎映画祭であれば、自分の思いを受け取ってくれると感じたに違いない。
授賞式への出席だけではなく、シネマテークの上映でも俳優や監督が頻繁に舞台あいさつに訪れる。中には上映期間中、ずっと高崎に宿泊してファンと交流する監督もいる。最近では、小栗康平監督も舞台あいさつに来館した。2月のプレ映画祭企画では、山田洋次監督も登壇した。また、緒方明監督がシネマテークで映画塾を開催し、映画の見方を講義することもあった。
高崎を訪れた監督、俳優たちが、志尾さんや小林さんに案内され、パスタやカツ丼談義をしながらまちなかの名物飲食店を楽しみ、ラジオ高崎に出演して映画について語っていく。授賞式でオダギリジョーさんが高崎ハムの話をする。こんなまちが他にあるだろうか。
●フィルム映画を継承する街景
「映画の街高崎」の魅力は、映画に対するプロフェッショナルな切り口と言える。2月に行う第30回高崎映画祭のプレ企画では、35ミリフィルムの作品に焦点をあて、昭和歌謡の名作を上映するとともに、全国のコミュニティシネマによるプロジェクトとしてフィルム映画のシンポジウムを高崎で開催する。山田洋次監督をゲストに全国の映画研究者が高崎電気館に集まる。また、映画のデジタル化が進み、フィルム映写の機会が少なくなっていることから、映写技師のためのワークショップも開催する。
高崎には、電気館、音楽センター、シネマテークに35ミリフィルム映写機があり、全国屈指の現役映写機を備える。そして第30回高崎映画祭の特別賞「高崎映画礎賞」受賞者で、長く高崎映画祭を映写技師として支えてきた小田橋淳夫さんは、フィルム映写の超ベテランである。昭和33年から高崎銀星座で働き、その後、高崎市職員として群馬音楽センターの映写、照明の仕事に携わってきた。
昭和の趣を残す電気館で、懐かしい映画を味わうだけでなく、フィルムという映画文化を次代に継承する上でも、高崎は大きな役割を果たすまちである。
●映画が生まれる街
「高崎フィルム・コミッション」が関係した作品で、この春の大きな話題となるのが橋本環奈さん主演「セーラー服と機関銃―卒業―」の封切りだ。
昨年4月から5月にかけ、高崎に縁のある人気作家、吉永南央さんの「紅雲町珈琲屋こよみ」と横山秀夫さんの「64」が高崎ロケのNHKドラマとなった。これまでも高崎で撮影された映画として、「半落ち」、「時をかける少女」、「包帯クラブ」、「ALWAYS三丁目の夕日’64」が知られる。
協力作品は、枚挙にいとまがなく、「高崎フィルム・コミッション」は多くの実績を上げている。高崎のまちなかで、撮影現場に遭遇し、人気スターを目の当たりにしたという話題が聞こえることも多い。情報が漏れるとファンが殺到して大パニックになるような大物スターの撮影は、高崎某所で秘密裏に行われているという。
カメラを通すと高崎は様々な都市に変化し、高崎とはわからない作品も数多いが、3月に公開される「セーラー服と機関銃―卒業―」は、高崎市民が見れば、一目で高崎とわかるオール高崎ロケの映画だという。高崎市民にとっても大いに注目したい作品だ。この映画の撮影は昨年の夏で、フィルムコミッションのスタッフも汗だくになって支援した。
「高崎フィルム・コミッション」は、高崎映画祭の人たちが長く必要性を訴えてのもので、平成14年に高崎市役所内に設置された。当初は、高崎のイメージアップや活性化を目的としていたが、担当者の情熱と親身な対応で評価が高まり、映画業界内でブランド力を持つ高崎映画祭との相乗効果で、この頃から「映画の街高崎」の発信力が高まった。高崎ロケの話題作が誕生し、高崎で撮影したいという要望も強い。
高崎市からフィルムコミッションの業務が「たかさきコミュニティシネマ」に移管され、本格的に関わるようになった志尾さんは、「撮りたい映像がわかり、支援にも一層力が入る」という。
映画が撮影された場所はファンから「聖地」と呼ばれ、「聖地巡礼」と称してまちなかのロケ地を巡る人たちもいる。ロケ地現場の写真を撮ってインターネットで発信するのが彼らの何よりの楽しみである。
●高崎映画祭は奇跡の「高崎ブランド」
全国でも、市民が主催運営している映画祭は少なく、その事業規模や30年という継続年数、知名度、多彩な活動は、日本を代表する映画祭といえる。
「映画の街」とうたっているまちは多い。そして規模は様々だが、映画祭を開催したり、市民が上映会を自主開催したりして、映画でまちづくりという取り組みも、よく聞かれる。かつて庶民の日常的な娯楽の場所であったまちなかの映画館が消え、往時のノスタルジーとともに映画を語り合う場を再生する作業は、理解を得やすいし、価値がある。一方、映画は家庭で手軽に楽しめるようになり、レンタルDVD、インターネット配信やBS放送の普及もめざましい。映画館というのは最新の3D、4D機能を備えたショッピングモールのシネコンという大きな流れの中で、映画をまちなかの文化として取り戻すことは、極めて困難と言えるだろう。
高崎映画祭やシネマテーク、高崎電気館はまさに奇跡的な事業と言え、企業のビジネスモデルと重ね合わせても興味深い。大型店(=シネコン)にはできない独自の品揃えと商品知識(=何百の映画を観て選ぶ個性的な映画のラインアップ)、東京100キロ圏にある高崎の交通利便性を生かした顧客のセグメンテーション(=映画ファンの広域集客と業界に特化した撮影支援)、生産者との連携ネットワーク(=監督・俳優との深いつながりと信頼)、専門的な技術力の蓄積(=映画への造詣・35ミリ映写機技術)に見事に成功し、高いブランド力を発揮している。
●高崎映画祭を支える高崎の力
高崎映画祭の財政はチケット収入、企業協賛、行政支援が三本柱で、応援を続けている高崎経済界の力は偉大だ。高崎映画祭もシネマテークも知名度は高いが、その知名度、ブランド力に見合う入場者があるかといった苦労を抱えているのではないだろうか。
高崎映画祭の期間中、仕事が終わって赤ちょうちんに出掛けてみようかと思った時、ちょっとその前に高崎映画祭の会場で、映画を一本観てはどうだろうか。映画が終わって、行きつけの店の暖簾をくぐったら、ビールを注いでくれるおかみさんに、観てきた映画の話しをしてみよう。その光景を、高崎に撮影に来ている映画スタッフが見たならば、きっとこう言うだろう。「やっぱり高崎の人は映画がわかってるね」。
(商工たかさき・平成28年2月号)