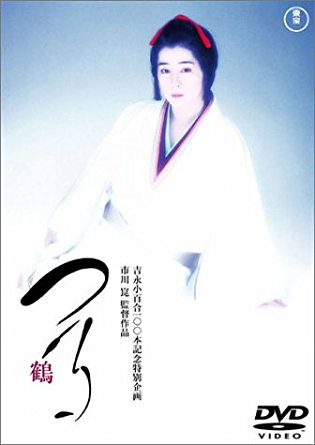47.高崎新風土記「私の心の風景」
春のきざしを求めて ―濠端を歩く―
吉永哲郎

立春を過ぎますと、こころなし春のきざしを探したくなります。こうした時、私は濠端をよく散策します。濠端の木々や水に映しだされる風景から、季節のさきがけを探し求めます。特にまだ咲く気配はないのに、桜の蕾のふくらみが気になります。
吉田兼好の『徒然草』「百五十段」は、中世の下克上(げこくじょう)(地位の下の者が上の人をしのいで勢いをふるうこと)の時代を、四季の移ろいから論じた段ですが、その文中に「木の葉の落つるも、まづ落ちて芽ぐむにはあらず。下よりきざしつはるに堪へずして落つるなり」ということばがあります。つまり葉が落ちて芽が出るのではなく、葉の下の春のきざしにこらえられなくて、散るというのです。この兼好法師の考えにそって冬の枯れ木をみますと、その梢は単なる棒線ではなく、細かいこめつぶ状の点があります。枯れ木ならばこうした点はないということになります。
あたりまえの事ですが、自然のいとなみを通して、時代や人間のありさまを見て取るとは、さすが兼好さまだと思わずにはいられません。濠端の散策は、単に風景に親しむだけでなく、こうした兼好さまとの出会いがあるので、癒されます。
そういえば濠の全面凍結した風景が見られなくなりました。以前、春先の柳川町の北の濠は凍結して、スケートをする人で賑わったものでした。まさに、地球温暖化を物語っているように感じます。
- [次回:春は椿の花から]
- [前回:「おらが春」― 一茶のこと ―]