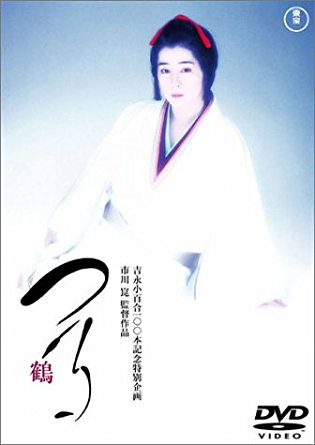69.高崎新風土記「私の心の風景」
屋敷神をまつるこころ
吉永哲郎

十二月に入りますと、「はやいものだ、一年もおわりか」と、なんとなくせわしい気持ちになります。こうしたことは昔の人も同じで、特に吉田兼好の『徒然草』の「折節の移りかはるこそ」(第十九段)に、その気特ちが伝わってきます。兼好は季節がつぎつぎに移り変わってゆく風情に趣があると述べていますが、特に年末の頃のことを「年の暮れはてて、人ごとに急ぎあへるころぞ、またなくなくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の寒けく澄める、廿日(はつか)あまりの空こそ、心ぼそきものなれ」と記し、年末の忙しい時、ふと月末の月を見ると、一年を振り返り感慨深いと述べています。
当時は陰暦ですので、月の姿がそのまま月の日にちを意味しています。月末は月の出も遅く、光も薄く感じます。また、大晦日について「亡き人のくる夜とて魂(たま)まつるわざは、このごろ都にはなきを、東(あずま)のかたには、なほする事ありしこそ、あはれなりしか」と述べています。兼好のいう大晦日に先祖の魂をまつる習俗を今はみかけませんが、十二月になりますと家の片隅にある「屋敷神」(ヤシキイナリ、屋敷の地主神、先祖霊などをいいます)の祠(ほこら)を飾りたてる家が今でもあります。
先日、清水寺石段登り口の石畳付近のお宅でみかけました。そういえば明治生まれの母が、大晦日の月に手を合わせていたことを思い出します。ともに古風な東の人の心を、今に伝えていると感じます。