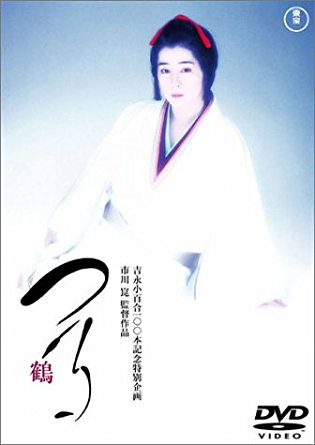111.高崎新風土記「私の心の風景」
木の下暗がりゆく
吉永哲郎

6月は鬱陶しい雨の季節だと口にしますが、この頃のことを、『和泉式部日記』には「木の下暗がりもてゆく」頃と表現し、「夢よりもはかなき世の中」、つまり恋の嘆きの日々になったと、記しています。
「木の下暗がり」とは、冬には葉が落ち木の下が明るかったのに、春になると新芽が出、だんだんと色濃く葉が繁り、木の下が暗くなっていくことをいいます。その昔この「木暗がりの季節」に、女性は聖女五月女<さおとめ>になるために、一定期間の物忌み籠もりをしました。そして聖女の資格を得た五月女が、早苗を植えました。この田植えの時期、男は聖女となった女性たちには逢えず、ある意味で一年のうちでもっとも異性に関心を寄せる季節、「恋の季節」の到来を意味していました。
こうした農耕儀礼を離れ、梅雨を「恋の季節」と捉え、王朝の男たちを描いたのが、源氏物語の「帚木」の巻です。一夜、宮中宿直の光源氏を慰めようと、友人の頭中将、藤式部丞、左馬頭の3人が訪れ、女性談議に花を咲かせます。このことによって、別名「雨夜の品定め」といわれます。春の花の時期、烏川右岸の堤下、聖石橋から北の烏川緑地公園までの桜並木は見事ですが、6月は「木暗がり」の路になります。王朝の男たちにならって、木暗がりの路を散策し、梅雨の夜のつれづれには「好きなタイプは」などと、女性談議に花を咲かせたいものです。
- [次回:泳ぎを覚えた頃のこと]
- [前回:アカシアの花咲く]