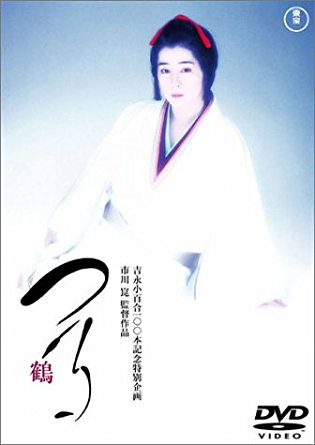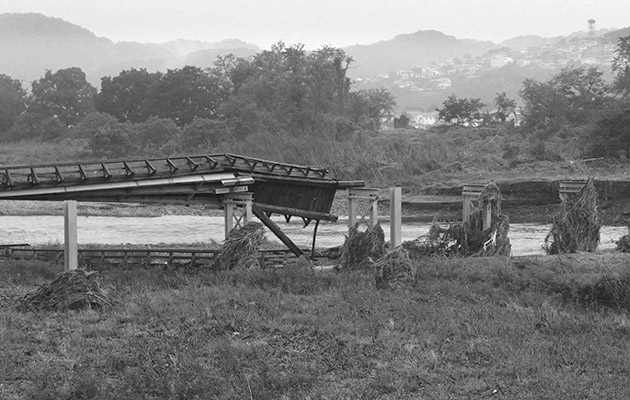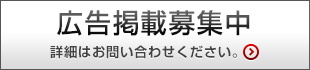古典花木散歩
11 をみなへし その2
吉永哲郎
前回の終わりに古今集掲載歌2首を紹介しました。今回は平安王朝時代の「をみなへし 」について記します。この時代は『能因歌枕』の「をみなへし、女をたとへて詠むべし」とあるように、「をみなへし」は直接女性をさしました。僧正遍照の歌「名にめでて折れるばかりぞ女郎花われおちにきと人に語るな」は、僧正遍照歌集には、女郎花が咲いている野で、馬から落ちた時に詠んだ歌とあります。この落馬の意に堕落の意を重ね、「女よ、私が落馬したことを、(私が女性に近づいて堕落したなどと)いふらすなよ」と、酒落た表現をしています。
源氏物語には女郎花を扱った場面が多くあります。今回は、薫君が六条院の女房を相手に、女郎花の歌を戯れに詠み交わす「蜻蛉」の巻の場面を紹介します。六条院は光源氏ゆかりの邸宅ですが、多くの女房たちが住まいしています。薫君は「私は色好み」ではないから、妙な気持ちをおこすことはないので、気軽におつきあいくださいと、女房たちに話しかけます。こうした時、老練な女房弁のおもとが、応対にでてきます。他の多くの女房たちは、薫君に遠慮して部屋の几帳(きちょう)のかげや隅に身を隠しています。薫君が 「女郎花乱るる野辺にまじるともつゆのあだ名をわれにかけめや」と呼び掛けますと、「花といへば名にこそあだなれ女郎花なべての露に乱れやはする」と弁のおもとがきりかえします。この歌の掛合の意味は、「女郎花」がどのような女性を象徴しているかを理解しないと、分かりません。
- [次回:12 をみなへし その3]
- [前回:10. をみなし]